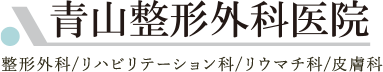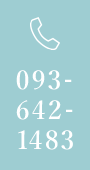足の痛みとは
 足(足首、足の甲、足の裏、足指)は、立つ・歩く・走る際に身体全体の重みを受ける部位であり、ちょっとした傷や障害でも身体全体のバランスを大きく歪めてしまい、深刻な症状の原因になる可能性があります。こうしたことから、足の怪我や障害は治癒だけでなく、全身の筋力や柔軟性をアップさせてバランスを調整し、機能を回復させるリハビリテーションが特に重要になります。
足(足首、足の甲、足の裏、足指)は、立つ・歩く・走る際に身体全体の重みを受ける部位であり、ちょっとした傷や障害でも身体全体のバランスを大きく歪めてしまい、深刻な症状の原因になる可能性があります。こうしたことから、足の怪我や障害は治癒だけでなく、全身の筋力や柔軟性をアップさせてバランスを調整し、機能を回復させるリハビリテーションが特に重要になります。
足の構造
足には多くの小さな骨が靱帯や腱に支えられ、他の部位に比べて筋肉が少ないという特徴を持っています。全身の重みを受け止め、着地などで大きな負荷を繰り返し受ける足は、日常の動作やスポーツ中の怪我が起きやすくなっており、筋肉が少ないことから脱臼や骨折リスクも高く、手術が必要になることも比較的多くなっています。
また、足はゆるいアーチ状の構造が縦横にあることで衝撃を分散させており、このアーチに異常があると足にかかる衝撃が増えて変形や痛み、怪我、転倒しやすいなどのトラブルを起こしやすくなります。
主な症状
- 足関節に強い痛みがある
- 立ち上がる・歩きはじめる際に足に強い痛みが起こる
- 坂道を歩くと痛みが起こる
- つま先立ちができない
- くるぶしの外側・内側に痛みがある
- 足に腫れがある
- 足に皮下出血がある
- 足に変形がある など
捻挫では症状の内容や経過が患者様によってかなり違うことがあります。痛みに腫れが伴うことが多いのですが、痛みだけで腫れがないケースもあります。また短期間で痛みが治まることもありますが、徐々に強くなっていくこともあり、注意が必要です。
代表的な疾患
足関節捻挫・足関節骨挫傷・
足関節(脱臼)骨折
足関節の骨折や捻挫は、主に転倒などの際に足首を内側にねじことで生じます。スポーツ中や日常でも起こり、捻挫や骨折では靱帯の損傷も伴います。靱帯損傷は、伸長、一部断裂など個々のケースで程度や範囲が異なり、靱帯に強く引っ張られて骨の剥離による骨折になるケースもあり、重篤な損傷を受けた場合は皮下出血によって患部が青紫になることもあります。
しっかり治療を受け、リハビリテーションに取り組まないと足首が不安定な状態が続いてしまい、軟骨が減少したり、変形性足関節症に進行したりなどに進行してしまう可能性もあります。足首が不安定な状態は全身のバランスを大きく崩す原因になり、転倒リスクも上昇させますので、足関節に問題がある場合にはできるだけ初期に適切な治療を受け、しっかり治すことが重要です。
骨折を起こしていない捻挫でも、シーネやギプスによる固定、松葉杖の使用で、腫れや痛みをより早く改善できるケースもあります。またX線検査では発見できない微細な骨折や、内出血や重い炎症を伴う骨挫傷では、超音波(エコー)検査などで軟部組織などの状態もしっかり確かめ、状態にきめ細かく合わせた治療やケアが重要になります。
アキレス腱断裂
ふくらはぎの筋肉とかかとの骨を結んでいるアキレス腱は足首の後ろの目立つ位置にあって、急激で大きな動きで特に強い負担を受けます。しばらく運動をしていなかった方が強い運動をした場合にアキレス腱断裂を起こしやすいことから30~50代の発症が多いですが、お子さまの発症も少なくありません。アキレス腱や周囲の損傷などの状態を詳細に観察・分析することが適切な治療には不可欠であり、当院では丁寧な診察や超音波(エコー)検査で正確に状態を把握して診断しています。ギプス固定などの保存的治療と断裂した腱を縫う手術があり、状態だけでなく、患者様のライフスタイル、年齢、スポーツとの向き合い方、既往歴などにより適した治療法は異なります。保存的治療では、筋力低下や可動域制限を起こしやすく、断裂の再発リスクが比較的高くなりますので、治癒後もしっかりケアやフォローを行うことが重要です。なお、アキレス腱断裂では、保存的治療の場合もできるだけ早期にリハビリテーションを開始することで高い効果を得られることが分かってきています。手術を受けた場合も、より早い回復と後遺症軽減には適切なリハビリテーションが必要です。当院では医師と連携した理学療法士が丁寧なリハビリテーションを行っており、より早い復帰を視野に入れたメニュー作りやきめ細かい指導も行っています。
変形性足関節症
過度な負荷による軟骨の摩耗や、捻挫や骨折などの外傷によって足の骨の変形が起こっている状態です。骨折が正しく治癒していないと関節にかかる負担が変わり、骨の変形を悪化させることがあります。立つ・歩く・走るといった基本的な動作で全体重がかかる足は、ちょっとした障害でも重心や全身のバランスに大きな影響を及ぼします。足に怪我をした場合には、軽度でも早めに受診してしっかり治しましょう。
外反母趾・扁平足
ハイヒールなど合わない靴を履き続けると、特定の位置に強い負荷がかかり、足の骨の配置が乱れ、足の親指の付け根にある中足骨は内側にねじれ、指先は外側にねじれる外反母趾という足の変形を起こします。足は多くの骨が靱帯でつながって縦横にゆるいアーチを描いており、それによって着地などから受ける衝撃を軽減しています。変形してアーチが崩れてしまうと足が着地などの衝撃を強く受け、強い痛みや変形の進行を起こし、悪化した場合には手術が必要になることもあります。なお、外反母趾は、加齢でも生じることがあります。
扁平足は足のゆるいカーブが失われている状態であり、後脛骨筋に先天的な問題があって生じていることもあります。
痛風
 遺伝的素因と生活習慣によって発症する高尿酸血症によって引き起こされるのが痛風発作です。痛風発作は血中の過剰な尿酸が鋭い針状の結晶になって関節にたまり、炎症を起こしている状態であり、歩行ができないほど激しい痛みを起こします。発症時には痛み止めや抗炎症薬による対症療法は可能ですが、高尿酸血症の診断や治療は痛みが改善してから行います。血液検査で尿酸値を調べ、X線検査で関節の状態を確認し、結果に応じた生活習慣の改善や薬物療法を行います。尿酸値が急激に上下すると痛風発作を誘発しますので、慎重なコントロールが必要です。また、尿酸値が下がってからも、しばらく治療を続けないと関節にたまった尿酸結晶が溶けないので、医師の指示を守って治療を続け、定期的に検査を受けましょう。なお、高尿酸血症は腎臓の機能を低下させる疾患ですので、痛風発作がない場合でも尿酸値が高いと指摘されたら治療が必要です。軽度の場合には生活習慣の見直しや十分な水分摂取などで改善できるケースもあります。
遺伝的素因と生活習慣によって発症する高尿酸血症によって引き起こされるのが痛風発作です。痛風発作は血中の過剰な尿酸が鋭い針状の結晶になって関節にたまり、炎症を起こしている状態であり、歩行ができないほど激しい痛みを起こします。発症時には痛み止めや抗炎症薬による対症療法は可能ですが、高尿酸血症の診断や治療は痛みが改善してから行います。血液検査で尿酸値を調べ、X線検査で関節の状態を確認し、結果に応じた生活習慣の改善や薬物療法を行います。尿酸値が急激に上下すると痛風発作を誘発しますので、慎重なコントロールが必要です。また、尿酸値が下がってからも、しばらく治療を続けないと関節にたまった尿酸結晶が溶けないので、医師の指示を守って治療を続け、定期的に検査を受けましょう。なお、高尿酸血症は腎臓の機能を低下させる疾患ですので、痛風発作がない場合でも尿酸値が高いと指摘されたら治療が必要です。軽度の場合には生活習慣の見直しや十分な水分摂取などで改善できるケースもあります。
足の慢性的な障害
(オーバーユース症候群)
酷使によって足に様々な障害や損傷が起こります。特に、柔軟性や筋力が不足していることが原因で起こりやすく、患部や状態によって診断名が変わりますが、総称としてオーバーユース症候群と呼ばれています。特に腱が障害されやすく、アキレス腱や後脛骨筋付着部の炎症が多くなっています。治療に加え、物理療法や運動療法といったリハビリテーションでより早い治癒を目指します。また、全体のバランスを考慮し、負荷を軽減させるトレーニングは、再発予防にも役立ちます。
足のスポーツ障害
シーバー病
かかとの後方に痛みが生じる障害で、スポーツに熱中しているお子さまの発症が多くなっています。お子さまの場合、生活への支障と成長への悪影響が及ばないよう考慮した治療やケアが重要になります。
足底腱膜炎
 かかとの骨の下側、少し前の位置にある足底筋膜付着部に痛みを生じます。足のアーチ構造の崩れ、着地の際の強い衝撃、アキレス腱による過度な牽引など、様々な負荷によって生じます。早期の治療が重要であり、当院では患者様の状態やライフスタイルなどに合わせて、装具療法、インソール、理学療法による治療などから最適なメニューを組んで治療しています。早い回復や再発予防に役立つストレッチ指導なども丁寧に行っています。
かかとの骨の下側、少し前の位置にある足底筋膜付着部に痛みを生じます。足のアーチ構造の崩れ、着地の際の強い衝撃、アキレス腱による過度な牽引など、様々な負荷によって生じます。早期の治療が重要であり、当院では患者様の状態やライフスタイルなどに合わせて、装具療法、インソール、理学療法による治療などから最適なメニューを組んで治療しています。早い回復や再発予防に役立つストレッチ指導なども丁寧に行っています。
診断
X線検査
 骨折や変形、骨形態の異常の有無や状態を詳細に調べ、壊死や腫瘍性病変がないかもチェックします。リウマチ性の変化を確認する際にも行われます。
骨折や変形、骨形態の異常の有無や状態を詳細に調べ、壊死や腫瘍性病変がないかもチェックします。リウマチ性の変化を確認する際にも行われます。
超音波(エコー)検査
 X線検査では確認が困難な筋肉、靱帯、腱をはじめとした軟部組織の状態や炎症について詳細な観察や分析が可能です。リアルタイムの状態をみることができ、動作した際の状態も確認できます。
X線検査では確認が困難な筋肉、靱帯、腱をはじめとした軟部組織の状態や炎症について詳細な観察や分析が可能です。リアルタイムの状態をみることができ、動作した際の状態も確認できます。
MRI検査
内部の組織をより精密に調べることができる検査です。X線検査では観察が困難な微細な骨折や骨挫傷なども正確に把握できます。必要な場合には連携している高度医療機関をご紹介しています。
治療
安静
足には大きな負担がかかり、その負担を他の部位に逃がすことができないことから、シーネやギプス、サポーターによる固定が有効です。また、負担軽減のために松葉杖を使用することで、より早い回復も期待できるケースがあります。
薬物療法
 強い痛みや炎症がある場合には鎮痛薬の処方を行います。
強い痛みや炎症がある場合には鎮痛薬の処方を行います。
理学療法や物理療法
できるだけ早期に適切な物理療法を受けることで、炎症をより早く改善できる可能性が高くなります。炎症が消えれば痛みなどの症状も軽減します。状態が落ち着いてきたら運動療法を行います。柔軟性を高めるストレッチやバランス良く鍛える筋力トレーニングなどをしっかり行って余計な負荷がかからないようにすることが再発防止にも役立ちます。
装具治療
足の変形などを伴う疾患では、装具療法が大きな改善効果につながるケースがあります。インソール(足底板)は、靴からの刺激の軽減、着地の際の衝撃緩和など、様々な効果が期待できます。特に外反母趾や扁平足では、患者様の足の状態にきめ細かく合わせた装具の使用が症状軽減と変形の改善に有効であり、装具の専門家と相談しながら最適な装具を作成しています。
姿勢指導
姿勢が悪いと特定の場所に過度の負担がかかり、治癒を妨げ、足の状態が改善しても再発リスクが高いままになってしまいます。姿勢や歩き方などを見直して正しい姿勢や動作を身に付けることで、より早い治癒や再発予防に役立ちます。
足の疾患は、
治療終了後のセルフケアが
大事です
 歩く・立つというのは日常での基本的な動作ですので、治療中でも足への負荷をゼロにすることは難しく、再発しやすい傾向があります。足のゆるいアーチ構造を正常に保つためには、適切な治療や変形を抑える処置が必要です。治療で状態が改善してからもリハビリテーションやセルフケアを続けましょう。また、痛みや不快感が現れたら速やかに受診することも重要です。
歩く・立つというのは日常での基本的な動作ですので、治療中でも足への負荷をゼロにすることは難しく、再発しやすい傾向があります。足のゆるいアーチ構造を正常に保つためには、適切な治療や変形を抑える処置が必要です。治療で状態が改善してからもリハビリテーションやセルフケアを続けましょう。また、痛みや不快感が現れたら速やかに受診することも重要です。
よくある質問
動脈硬化による足の痛みは
どんなものでしょうか?
動脈硬化が進行すると、足に痛みを引き起こすことがあります。特に、間欠性跛行や安静時痛といった特徴的な症状が現れることが多いです。
これらの症状は、**閉塞性動脈硬化症(ASO)**という病気に関連しており、足に血液を供給する血管の動脈硬化が進行することで発生します。
間欠性跛行(かんけつせいはこう)
症状
ふくらはぎや太ももが重く感じたり、痛くなったりする症状が現れます。
少し歩いただけで痛みを感じることが多く、休み休みしか歩けなくなることがあります。
特徴
上り坂や階段を上る時に、特に症状が強く現れることがあります。歩行中に足の痛みを感じるため、日常生活に支障をきたすことがあります。
安静時痛(あんせいじつう)
症状
じっとしていても足が痛む場合があります。特に夜間、痛みが強くなり、眠れなくなることもあります。
特徴
刺すような痛みが持続することが特徴です。
動脈硬化による足の痛みの原因
動脈硬化が進行すると、足に血液を送る腸骨動脈や大腿動脈が狭くなり、血流が不足することで足に十分な酸素が届かなくなります。
この状態が続くと、痛みやしびれなどの症状が現れることがあります。
改善方法と予防策
生活習慣の改善
健康的な食事や適度な運動を心がけ、血管の健康を保ちましょう。特に禁煙や塩分の摂取制限が重要です。
薬物治療
血流改善のために、血液をサラサラにする薬を使用することがあります。これにより血管が広がり、血流が改善されます。
足のケア
足を温める、マッサージをする、適切な靴を選ぶなど、足のケアを行うことも大切です。
足がズキンズキン痛む原因は
何ですか?
足がズキンズキンと痛む原因は多岐にわたります。筋肉痛や神経痛、骨折、感染症、痛風など、さまざまな状態が足の痛みを引き起こします。
痛みが続く場合や原因が不明な場合は、医師の診断を受けることが重要です。
筋肉痛
原因
普段しない運動や過剰な運動をした際に、筋肉が損傷し、その修復過程で炎症が起こります。
特徴
急に強い運動をした後に感じることが多く、痛みは運動後24〜48時間以内に現れることがあります。
加齢によって炎症反応が遅れるため、痛みが遅れて現れることもあります。
神経痛
原因
神経が圧迫されることにより、痛みやしびれが発生します。
特徴
痛みの感じ方が個人差が大きく、しびれや感覚異常を伴うことが多いです。
神経痛は、坐骨神経痛など、特定の神経が影響を受ける場合に発生します。
骨折
原因
足を強く打ったり、転倒したりすることによって骨折が起こることがあります。
特徴
足の甲やかかとに痛みがあり、腫れやあざが現れることがあります。骨折が疑われる場合は、レントゲンでの確認が必要です。
感染症
原因
細菌感染が原因で発生することがあり、蜂窩織炎や化膿性関節炎などが代表的です。
特徴
足の腫れや発赤が見られることがあり、発熱を伴う場合もあります。感染症が疑われる場合は、早期の治療が重要です。
痛風
原因
体内の尿酸が過剰に溜まり、結晶化して関節に沈着することで痛みが引き起こされます。
特徴
足の指やその周囲に強い痛みを感じ、特に夜間に発症することが多いです。
その他の原因
外反母趾
足の親指が内側に曲がり、痛みを引き起こす疾患です。
強剛母趾
足の親指の関節が硬直し、歩行時に痛みが生じます。
関節リウマチ
自己免疫疾患で、足の関節に炎症を引き起こすことがあります。
足底筋膜炎
足底の筋膜に炎症が生じ、かかとから足指にかけて強い痛みを感じます。
骨粗しょう症
骨の密度が低下し、骨折しやすくなり、足の痛みが現れることがあります。
腰椎症
腰の骨に変形が生じ、足に放散する痛みを引き起こすことがあります。
くる病・骨軟化症
骨が軟らかくなり、変形や痛みが発生することがあります。
足の痛みを予防・改善するための対策
- 適度な運動を心がけ、足の筋肉を強化しましょう。
- 正しい姿勢や歩き方を意識し、足に負担をかけすぎないようにしましょう。
- 足のケアを定期的に行い、靴の選び方にも注意を払いましょう。
心筋梗塞の前兆は足に現れる?
心筋梗塞が発症する前に、さまざまな前兆が現れることがあります。足の冷感やしびれ、痛み、こむら返りといった症状が出ることもありますが、これらは心筋梗塞そのものの前兆ではなく、むしろ末梢動脈疾患などの循環器系の問題を示唆している場合が多いです。
心筋梗塞の前兆に見られる症状
心筋梗塞の前兆として、以下の症状が現れることがあります。これらの症状が同時に現れる場合、特に注意が必要です。
心筋梗塞の危険信号として、胸の痛みや息切れが繰り返し発生する場合には、早急な医療機関の受診が推奨されます。
- 胸の痛みや不快感
- 息切れや冷や汗
- 吐き気や不安感
- めまい、肩や腕の痛み
- 背中の痛み、顎の痛み
足の動脈硬化と心筋梗塞の関連
心筋梗塞と末梢動脈疾患は密接に関連しており、下肢閉塞性動脈硬化症が進行すると、足に冷感やしびれ、痛みが現れることがあります。これらの症状が悪化すると、歩行が困難になる間欠性跛行や、安静時に痛みが続く安静時疼痛が起こることもあります。最終的には、潰瘍や**壊疽(えそ)**が発生するリスクが高まります。
心筋梗塞や狭心症の検査方法
心筋梗塞や狭心症が疑われる場合、以下の検査が行われることが一般的です。
これらの検査によって、心臓の状態や冠動脈の閉塞状況を詳細に確認することができます。
- 心電図(ECG)
- 胸部レントゲン検査
- 心臓超音波検査(エコー)
- 血液検査
- 冠動脈造影検査
足の血流が悪いとどんな症状が
出る?
足の血流が悪くなると、さまざまな症状が現れ、健康に深刻な影響を与える可能性があります。
血流障害は主に動脈硬化が原因であり、進行すると歩行障害や皮膚の問題を引き起こすことがあります。
足の血流障害による症状
足が冷たくなる
血流が悪くなると、足先やふくらはぎが冷たく感じられることがあります。
皮膚や爪の色が変化する
足の皮膚や爪が白や青、赤紫に変色することがあります。
歩行時に痛みが出る(間欠性跛行)
歩いているとふくらはぎなどが痛み、休息を取ると痛みが治まることがあります。
安静時痛
じっとしている状態でも足に痛みを感じることがあります。
潰瘍や壊死の発生
血流不足が進行すると、足に潰瘍や壊死が現れることがあります。
足のつりやすさ
血流が悪くなることで、足が頻繁につることがあります。
足の血流障害の原因:動脈硬化とその進行
足の血流障害は、主に動脈硬化によって引き起こされます。動脈硬化が進行すると、血管が狭くなり、血流が悪化します。その結果、歩行障害や潰瘍、壊死などの深刻な症状が現れます。特に、糖尿病や喫煙などのリスク因子がある場合、血流障害は重症化しやすくなります。
血流障害の治療法と予防
血流障害が進行して重症化すると、足の切断が必要になる場合もあります。しかし、早期に適切な治療を受けることで、症状を緩和し、進行を防ぐことが可能です。治療方法としては、血行再建手術や薬物療法が考慮されます。さらに、生活習慣を見直し、禁煙や血糖管理を行うことが予防に繋がります。